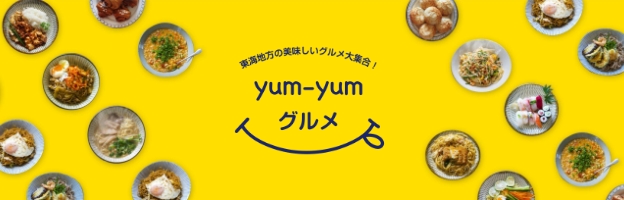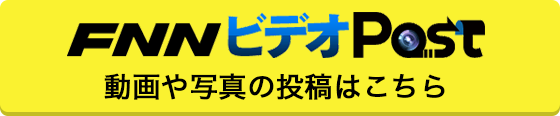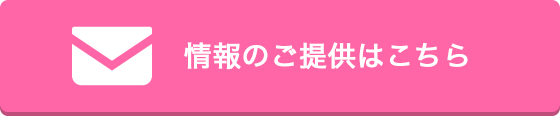明治用水の漏水問題で、改めて水の大切さが認識されています。いざという時でも水を確保できるよう地下水を活用している、名古屋市中川区の病院の取り組みを取材しました。
掖済会病院の熊谷医師:
「特に味も問題ないですし、健康にも害はないと思います」
名古屋市中川区の掖済会病院。医師がコップに注いだのは井戸水、地下からくみ上げられた水です。
災害拠点病院でもあるこの病院では、いざという時に備えて、普段から敷地内の地下水を利用しています。
先週、豊田市の明治用水で起こった大規模な漏水。大きな混乱が続いています。
一般的な病院で使われているのは主に水道水ですが、水源のトラブルに限らず地震などで断水が起きると、命に直結する問題になります。
熊谷医師:
「東日本大震災の時に、うちの病院の中で防災意識をもうちょっと高めなきゃいけないということで、ライフラインをしっかりと整えようと」
防災の観点から、掖済会病院では8年前に敷地内に井戸を堀り、病院施設で利用しています。
熊谷医師:
「ここから井戸水を汲み上げて、それをそのままこっちのタンクに一旦ためます。そのあとずっとろ過のシステムで水をきれいにするような形にして、きれいになったものがここにたまると。名古屋(市水道局)の水が止まったという場合でも、こっちの井戸水が基本的には使える」
井戸からくみ上げた水は、地上に設置したろ過装置で砂や細菌などを取り除いた後、水道水と混ぜ合わせて院内に送られます。
地下水と水道水の割合は8対2で、病院の水道水節約にも一役買っています。
浄化装置では常に水質の管理も行われ、年に一度は愛知県薬剤師会による簡易専用水道の検査で水の安全をチェックしています。
熊谷医師:
「今回の豊田の(漏水の)件がありましたけれども、(水が)使えなくなった時でも、最低限うちの病院が水を確保できるようなことを作っていくということは、防災の上では非常に大事かな思っています」
明治用水の漏水事故で改めて認識した水の重要性。病院に限らず古くからの給水手段である井戸水の活用が再び注目されています。