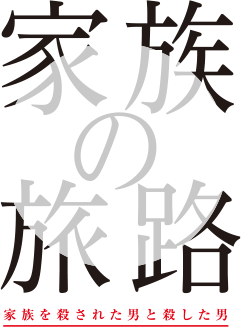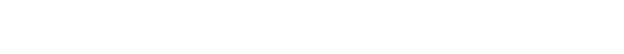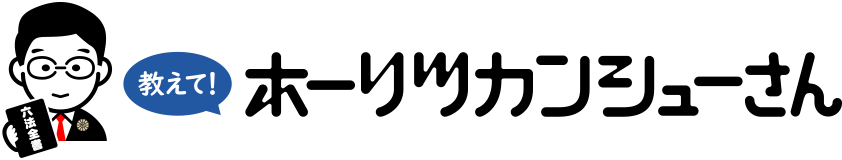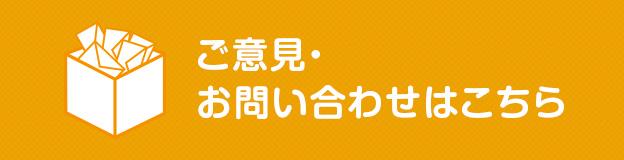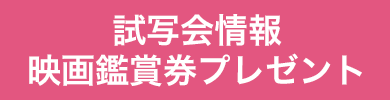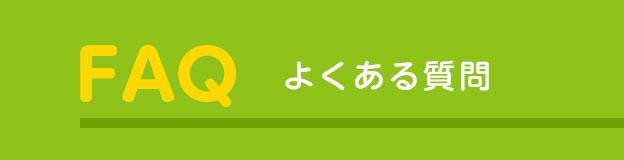第5回 「二回試験」
今回は、学生の皆さん必見!弁護士になるために必要な“ある試験”についてのお話です。
まず、皆さんは弁護士ってどうやってなるのか知っていますか?
「そりゃ、司法試験に受かればなれるんでしょ?」って思った方、それは半分正解です。
司法試験に受かると、その後「司法修習」という研修が始まり、これを1年間受けなければなりません。
そして、「司法修習」の最後に待ち構えている試験が、「司法修習生考試」通称「二回試験」。これに合格すると、晴れて法曹資格を得られるのです。
さて、その「二回試験」ですが、はたしてどんな試験なのでしょうか。
実はコレ、れっきとした国家試験なのです。
まず、試験科目は「民事裁判」「刑事裁判」「検察」「民事弁護」「刑事弁護」の5科目。
各科目100頁を超える問題文(記録)が渡されて、それを科目ごとに法曹三者の立場で分析させるような問題です(たとえば「刑事弁護」でしたら、弁護人として記録を分析するという問題になります)。
そして、試験時間は…1科目7時間半!「おいおい、じゃあ昼食はどうするんだ?」って思った方、大丈夫です。ちゃんと試験の途中に昼食時間は設けられています。
ただ、この時間には問題を解くことも許されているので、みんな問題を解きながら昼食を食べるのです。昼食は、ゼリーで済ます人からお弁当をしっかり食べる人までさまざま。これを5日間繰り返します。
合格不合格については、すべての科目の総合点での判定ではなく、1科目ごとに判定します。ですので、1科目でも不合格になると、その年は全部不合格。不合格になると一旦修習生を罷免(クビ!)されて、翌年全科目受け直しとなります。
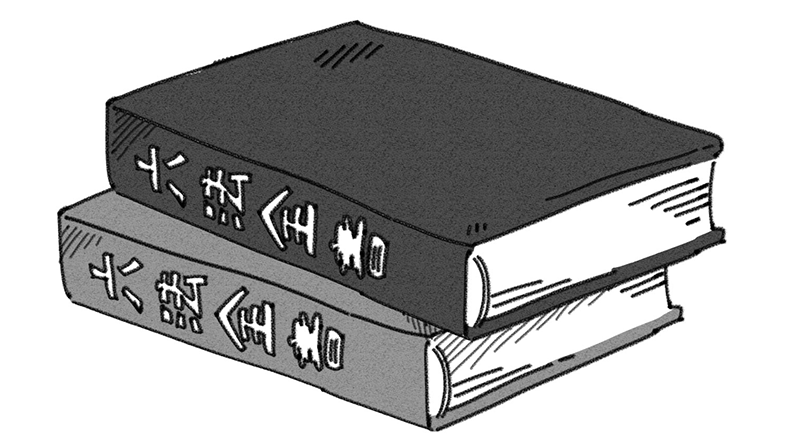
そして、ここが重要なのですが、試験時間内にひもを綴じられないと、どんなに素晴らしい答案でも問答無用で失格となるのです!何があろうとひもだけは綴じなければならないというわけです。
いかがですか?考えただけでもゆううつになるような…「恐怖の二回試験」と言われる所以です。
気になる合格率ですが…一番最近の試験で、99%近いと聞いています。不合格者は16名。その前の年の試験でも、不合格率は約3%、不合格者は約50名だそうです。
なんだ、案外受かるんだ…とホッとした人も多いと思いますが、受けてみると怖いんです、コレが。各科目が終わった後にミスが発覚すると、血の気が一気に引きます(まあ、余裕たっぷりな人もいますが。)。
結果発表は、不合格者発表という形で行われます。掲示板に自分の受験番号がなければ合格ということになります。
長く厳しい司法試験のことは聞いたことがあっても、二回試験のことは知らなかったという方が多いのでは?
浅利弁護士はどんな学生生活を送っていたでしょうね…司法修習生時代に、所長の澤田弁護士に出会ったと言っていましたよ。そんなことに思いをはせながら、ドラマを楽しんでみるのも面白いですね。