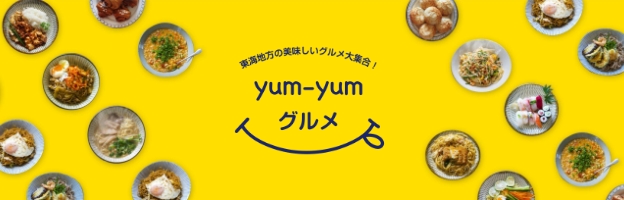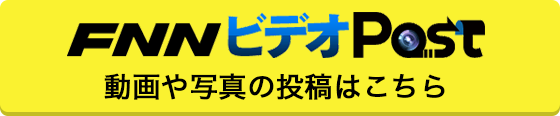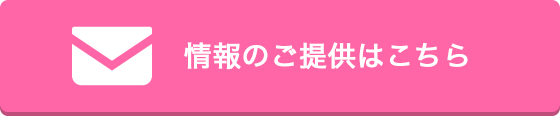司法を身近に感じてもらおうと始まり、この5月で10年、昨年までに全国で1万1千件以上、9万人近くの人が裁判員を経験しましたが 、市民からは「人の判決を決めるのは荷が重い」、「制度がよくわかっていない」などの声も聞かれます。
また、裁判員経験者からは、「途中で裁判に参加できなくなることへの不安」や「守秘義務が厳しい」など制度の課題も指摘されています。
■育児や仕事どうする 年々上昇する辞退率
名古屋市内で2人の子供を育てる、30代のA子さん。

A子さん:
「頭部と頸部を刺された事件だったので、刃物の構え方だったりとか、振り回し方だったりとか、そういったところを何度も話し合ったりしました」
裁判員裁判は原則、殺人や傷害致死など一定の重大犯罪のうち、地方裁判所での裁判で行われ、裁判官3人と裁判員6人が証拠をもとに話し合い、被告が有罪か無罪か、さらに量刑を決めます。

裁判所は事件について丁寧に分かりやすく説明し、話しやすい雰囲気だったという一方で、A子さんには “ある悩み”があったと言います。
「(裁判所が)保育園とかは準備して下さっているんですけれども 、例えば途中で病気になったらどうしようとか、熱出ちゃって、裁判に出られなくなったらどうしようとか、そういうのはすごく心配でした。やり始めると責任感も出てくるので、最後まで事件に関わりたい気持ちもありますし…」。
実は裁判所から選任の案内を受けながら、辞退する割合は開始当初から年々上昇しています。

2009年の53%から、去年はおよそ7割近く(67%)まで上がりました。
その背景には、A子さんと同じように裁判に参加している間に子供を預けられなかったり、選ばれても仕事を休みづらいという現状があります。
■「5日くらいと思ったら…」 長期化する審理期間
また、それ以外にも、辞退が増えやすい要因はあります。
おととし名古屋地裁で行われた裁判の裁判員を務めた、会社員のBさん。
Bさんは、当時19歳だった名古屋大学の元女子学生が、知人の女性を殺害したほか、高校時代にも、同級生の男女2人に劇物の硫酸タリウムを飲ませ殺害しようとした殺人未遂の罪など、合わせて7つの罪に問われた事件の裁判を担当しました。
Bさんたちが出したのは無期懲役の判決。しかし、判決を出すまでにはかなりの時間がかかったと言います。
取材でBさんは、びっしりと印が付けられたカレンダーを見せてくれました。平日のほとんどにつけられた丸印…。

Bさん:
「丸がついたところ全てが裁判の日。最初は本当に分からなくて、このうちのどこかだと思ったんですね、5日前後だと聞いていたので。よくよく読んだら、丸がついている日、全てにに参加していただくことになりますと書いてあったものですから、かなりびっくりした」
審理期間は1月16日~3月24日までの合わせて68日間にも及びました。Bさんは休みを取れましたが、長期間のため辞退者は多かったと話します。
「裁判員裁判の典型的な例が、3日~5日ぐらいと伺っていたんですけど、それくらいであれば融通効く職場の方は多いと思うんですよ。どうしても事件によって1カ月単位とか2カ月単位とか、もっと長いこともあると思うんですけど、ということになると現実的にはなかなか難しいのかなというところはありますね。そういう意味では、選任手続きの中で辞退される方が多かったと思うんですよ」。
初公判から判決までの審理期間…去年の平均は「10.8日」。これは、裁判員制度開始当初の3.7日のおよそ3倍の日数です。

最高裁がおととし、民間に委託して行った調査では、審理予定日数の増加が辞退率上昇に関係している可能性が高いと指摘しています。
■厳しい守秘義務…体験談を伝えることも
また、実際に裁判員を経験した人たちを悩ませる課題もあります。
ことし2月、東京都内で開かれた会合、会の名前はLJCC(Lay Judge Community Club)。

自分達の裁判員の経験について語る、裁判員経験者によるコミュニティーです。
不動産会社を経営する田口真義さん(43)が中心となって立ち上げました。
田口さん:
「声を上げたくても上げられない裁判員経験者の方、守秘義務の問題があったり、周囲からの反応を気にして表立っては話せない、あるいは自分が下した判断がどうだったかを思い悩む人がいらっしゃって、こういう方の声を受け止める器が必要と感じた。集まって茶話会のように話ができる環境があればいいなと」
会ではテーブルにお菓子も用意されるなど、和やかな雰囲気。裁判員経験者たちが、裁判での出来事について話し合います。
田口さん:
「(被害の)写真モロにだった人?」(ほぼ全員が挙手)
50代女性:
「ほぼほぼ全部血だったので、赤い服でしたね。上から下から全部…。私は、特にショックを受けたということはなかったです」
70代男性:
「私は首吊りの自分で自殺したように見せかけた事件だから。(写真は)モロだったと思う」
40代男性:
「どんな傷でもやっぱりショックを受ける方がいらっしゃると思う」
70代男性:
「目をそらしても結構ですと、必ず(裁判長から)アドバイスがありましたよね」
裁判員裁判では、評議の内容について罰則付きの守秘義務が課せられていて、裁判員経験者たちは、裁判の中で悩みがあっても声を上げづらいといいます。
この課題について、専門家は、守るべき部分を裁判所がはっきり示した上で、裁判員に体験談を広く語ってもらうことが大切だと指摘します。

南山大学法学部 岡田悦典教授:
「日本の裁判員制度の場合には、特に守秘義務というものを強く強調している側面があるかなと思いますね。
裁判員として体験した事柄を話すことは何ら問題ではありませんので、そういった経験者の意識とか、よかったこと、あるいは苦労したことでも構わないと思うんですけれども、感想はしっかりと体験談として伝えていくことは非常に重要ですね。
なので、話していいことは何かというのを積極的にきちっと明示すべきだと思いますし、何を話してはいけないのかということも、しっかりと例示して説明することも大事だと思います」
LJCCの田口さんは、裁判員経験後の2012年、全国50の地裁などに提言書を提出しました。

田口さん:
「知り合った裁判員経験者の方々と色々と議論して、当事者である経験者の意見も聞いてもらいたい。自分たちの思うところを表現してみようと…」
裁判員制度について、対象となっている刑事事件以外にもより身近な民事や行政訴訟にまで拡大すべきなど、13の提案をしました。
しかし、裁判所から回答はもちろん、連絡すらありませんでした。
田口さん:
「無回答であることが回答なんだろうな捉えていて、市民の感覚を取り入れようと表向きは言っているんですけれども、実際に自分たちはこう思うと伝えたところで、それは耳を傾けないわけですよね」
田口さんが見せてくれたバッジ、裁判員経験者全員に、贈られる記念品です。その箱には『裁判は皆さまの貴重なご意見に支えられています』と書かれていました。

田口さん:
「単純に矛盾ですよね。そう言っているんですけれども、その姿勢は決して謙虚でなく、虚心坦懐でもなく、かたくなに閉ざしているようなイメージで僕は受け止めています」
元々国民と司法を近づけるために始まった裁判員制度。開始から10年、掲げた市民感覚から離れ、いま曲がり角を迎えています。