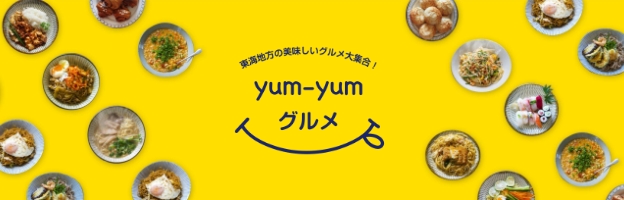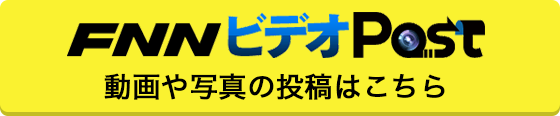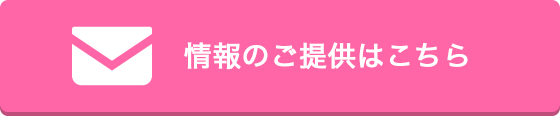5月末から6月にかけ、三重県で園児や小・中学生の感染判明が相次ぎました。変異ウイルスが広がっている現状での子供たちの感染リスクについて、感染症の専門家に訪ねました。
三重県では5月末から6月にかけ、保育園児の男女や小学生の女の子、中学生の男の子に感染が判明。いずれも「家族から感染した可能性」が疑われています。
「子供はかかりにくい」「重症化しにくい」とされてきましたが、変異ウイルスが広がっている現状ではどうなのか。愛知県がんセンター病院の伊東先生に「子供たちの感染リスク」について訪ねました。
まず、変異ウイルスの感染力は、子供だけでなく全年齢を対象に、従来型より強くなっているといいます。ただし、多くは無症状や軽症で、変異ウイルスの流行によって子供が重症化するというデータは確認されていないそうです。

厚生労働省によると、6月2日時点で19歳までの国内の死者数はゼロとなっています。(1万1003人中)
感染の経路については、子供の感染のおよそ7割が家庭内感染で、さらにその半数は父親経由だといいます。「職場などで第三者との接触が多い分、割合が高いのではないか」と伊東先生は話しています。

子供たちの感染を防ぐ一番のポイントは、大人が家庭内にウイルスを持ち込まないことです。家庭内感染を防ぐには「3密対策」「手洗い」「適切なマスクの着用」といった基本的な対策を続けることが重要です。
また、子供たちのマスクの着用について、伊東先生は「着用が望ましいが、2歳未満や障害のある子供の場合は、誤嚥や窒息の危険性があるため注意が必要。2歳以上でも、可能な限り保護者や学校の先生が見守ることが望ましい」と話しています。

なお、厚生労働省は、ファイザー社製のワクチンの公的な予防接種の対象年齢を、今後、現在の16歳以上から12歳以上に拡大することを決めました。

子供たちに接種した場合の安全性については、アメリカの研究データによると、接種を受けた12歳から15歳までの1131人に検査したところ、重い副反応は出ていないそうです。